製造業の分野でよく耳にする、機械保全技能士の資格。
スキルアップや転職活動のためなど、機械保全技能士の資格取得を考えている方は多いと思います。
しかし中には
「機械保全技能士ってどんな資格?難しいの?」
「機械保全技能士は役に立たないって聞いたけど本当?」
などと疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこでこの記事では、機械保全技能士とはどんな資格なのかを詳しくご紹介いたします。資格の種類や難易度、取得するメリットのほか、どんな人に向いているのかなどのお役立ち情報も交えながらわかりやすく解説していきますね。
【この記事でわかること】
・機械保全技能士とは?
・機械保全技能士の資格の種類と違い
・機械保全技能士資格が「役に立たない」といわれる理由
・機械保全技能士の資格を取得するメリットと活躍の場は?
・機械保全技能士に求められること
・機械保全技能士に向いている人の特徴
なお、記事の中で例として挙げるものは、それぞれ一部です。たくさんありますので代表的なものに絞っています。
機械保全技能士の資格に興味がある方はぜひご覧ください。
目次
機械保全技能士とは?
工場内の機械のメンテナンスを行うためには、専門的な技術や知識が必要となります。そうした機械メンテナンスの技術、知識を証明する国家資格が「機械保全技能士」です。
モノづくりの現場では非常に多くの機械が稼働しています。それらの機械は長く使い続けるうちに徐々に機能が落ちていき、時には故障してしまうこともあります。そうしたトラブルを未然に防ぐため、工場では定期的に機械のメンテナンスが行われています。
機械保全技能士の資格を取得することで、国の公的機関(厚生労働省)から、機械のメンテナンスに関して一定以上の技術と知識を有していると認められていることが証明できます。つまり「国が認めた専門家」であり、製造業の分野で非常に需要が高く活躍が期待できる資格と言えます。


機械保全技能士の資格の種類と違い
機械保全技能士の資格の種類は「4つの等級」があります。
より専門性が高い順に、特級、1級、2級、3級で、それぞれ以下のような違いがあります。
▼特級
保全に関わる業務の監督者として働く管理職の人を対象としている資格です。
▼1級
製造業の企業の保全部門などでリーダー的な役割を担っている人を対象としています。
▼2級
保全に関わる知識などを必要とする新入社員から中堅レベルの社員などが対象です
▼3級
初級レベルの知識やスキルの習得が求められる資格で、学生や新入社員などを対象としています。
ここからは、それぞれの試験問題の内容や受験に必要な条件、難易度について解説していきます。
機械保全技能士の試験問題の内容について
機械保全技能士の試験では、すべての等級で「学科試験」と「実技試験」があります。
【特級】
特級の学科試験では8科目が出題されます。
生産活動の流れや日程計画などに関する「工程管理」、作業の標準化や作業改善などに関する「作業管理」、品質管理の手法や検査方法などに関する「品質管理」、原価計算などに関する「原価管理」、労働安全衛生法や環境基本法などに関する「安全衛生管理及び環境の保全」、教育訓練やマネジメントなどに関する「作業指導」、設備の点検や保全計画などに関する「設備管理」、生産システムや工作法などに関する「機械保全に関する現場技術」の8科目です。
また特級の実技試験では7科目が出題されます。
「工程管理」「作業管理」「品質管理」「原価管理」「安全衛生管理」「作業指導」「設備管理」の分野で、それぞれ具体的な作業が行えることが求められます。
【1~3級】
1~3級の学科試験では共通科目5つに加え、選択制の科目1つが出題されます。
共通科目の5つは
「機械一般」「電気一般」「機械保全法一般」「材料一般」「安全衛生」です。
それに加え以下からいずれかの科目を受験者が選び、受験します。
▼1・2級
「機械系保全法」「電気系保全法」「設備診断法」のいずれか1つ
▼3級
「機械系保全法」「電気系保全法」のどちらか1つ
なお、これらの他に外国人技能実習生を対象とした「基礎級等」があります。基礎級等にも学科試験と実技試験があり、機械に関する基本的な知識や検査方法などの基礎問題が出題されます。学科試験は日本語で出題されるため、一定以上の日本語力も必要とされます。
受験方法や受験に必要な条件
ここからは機械保全技能士の受験方法と、受験するために必要な条件についてお伝えしていきます。まず機械保全技能士の受験方法からご紹介します。受験方法は以下のような流れとなります。
(1)申請
申請は受験者個人で行う方法と、団体内の申請をまとめて一括で行う方法があります。
いずれの場合でも、インターネット申請もしくは郵送での申請を選択できます。
(2)学科試験
学科試験は都道府県ごとに指定された会場で受験します。会場は47都道府県に1会場を目安に、県庁所在地もしくは地理的な事情や交通の便などを考慮した地区に指定されます。企業や学校などが指定される場合もあります。
(3)実技試験
実技試験も、学科試験と同様に各都道府県の指定会場で受験します。実技試験の共通科目は学科試験と同日に行われますが、選択制の科目の一部は別日程にて実施される場合もあります。
次に、機械保全技能士の受験に必要な条件についてです。機械保全技能士を受験するためには、等級により以下のような条件を満たさなければなりません。
【特級】
機械保全技能士1級に合格し、なおかつ5年以上の実務経験を持っていることが必要
【1級】
| 機械保全技能士2級合格者 | 2年以上の実務経験が必要 |
| 機械保全技能士3級合格者 | 4年以上の実務経験が必要 |
| 機械保全技能士の保有資格なし | 7年以上の実務経験が必要 |
※既定の学校を卒業していたり、職業訓練を修了していたりする人は,内容に応じて必要となる実務経験の期間が短くなります。
【2級】
| 機械保全技能士3級合格者 | 実務経験は不要 |
| 機械保全技能士の保有資格なし | 2年以上の実務経験が必要 |
※既定の学校を卒業していたり、職業訓練を修了していたりする人は内容に応じて必要となる実務経験の期間が短くなります。
【3級】
特に条件はなし。年齢学歴問わず受験可能です。
また、各試験の合格レベルと同等以上の能力が認められた場合には、試験の免除を受けることもできます。


機械保全技能士の資格試験の難易度と合格率
2025年3月25日時点で発表されている合格率で見ると、2023年の合格率は特級で19.7%、1級で33.8%、2級で39.5%、3級で76.4%です。全等級の平均で見ると45.2%。合格者は受験者の約半数以下ということになりますので、機械保全技能士の資格試験の難易度は高いと言えます。中でも特級の合格者は5人に1人以下で、非常に難易度の高い資格であることがわかります。
ただし機械保全技能士の試験を全体でみると、問題1つ1つはそれほど難しくない傾向にあると言われています。難易度が低めの3級からスタートし1つずつ知識を深めていけば、着実にステップアップを狙える可能性も高いでしょう。
難易度が高い特級や1級などは出題範囲が広く、豊富な知識が必要となるため、現場での作業や経験から得た知識だけで合格することは難しいとされています。実務経験が長い方であっても、過去問題に取り組みしっかりと対策を取ることが重要です。
機械保全技能士資格が「役に立たない」といわれる理由
機械保全技能士の資格について「現場では役に立たない」「取得しても転職では有利にならない」などの話を耳にし、取得するかを悩んでいる方もいるかもしれません。
専門性を証明する国家資格の機械保全技能士。なぜ「役に立たない」と言われることがあるのでしょうか?
それには主に2つの理由があります。
業務独占資格ではない
例えばアーク溶接の業務を行うためには、アーク溶接等の業務に係る特別教育を修了していることが義務付けられています。このように、その業務を行う際に必ず必要な資格を「業務独占資格」と言います。
機械保全技能士の主な業務は、機械のメンテナンスや点検です。機械のメンテナンスや点検を行うためには、必ずしも資格が必要なわけではありません。
こうしたことから「機械保全技能士は役に立たない」と感じる方も中にはいるようです。
知名度が低い
機械保全技能士の資格が役に立たないといわれる最も大きな要因として、一般的な知名度の低さが挙げられます。
機械保全技能士が活躍するのは、工場内など一般の人にとってあまり馴染みがない現場です。またその専門性の高さから業務の様子を一般の人が目にする機会も少なく、機械保全技能士の行う業務自体を知らない方も多くいます。
一般の人から見て身近に感じにくい、知りにくいという点から、知名度が低いという実情があります。
機械保全技能士の資格を取得するメリットと活躍の場は?
機械保全技能士の資格を持っていなくても、製造業で働くことや、機械のメンテナンスを行うことは可能です。「それなら、わざわざ機械保全技能士の資格を取る必要はないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし機械保全技能士の資格を取ることには、いくつものメリットがあります。ここでは、特に大きな『4つのメリット』をご紹介します。
専門性の高い仕事ができる
機械保全技能士を取得することで一定以上の技術や知識を証明できるので、より専門性の高い仕事を行う機会が得られます。
また社内・社外の信用度の高まりから、重要な業務を任されるようになったり、話をよく聞いてもらえるようになり提案がしやすくなったりと、日々の業務でもメリットを実感できることもあるようです。
製造業において幅広くニーズがある
前述したように、機械のメンテナンスには必ずしも資格が必要なわけではありません。とはいえ、機械や設備は工場にとって生命線です。多くのメーカーが、それら機械のメンテナンスを任せるなら専門性の高い人を選びたいと考えています。製造業でニーズを高めたいなら機械保全技能士はぜひ取得したい資格の1つであると言えるでしょう。
就職・転職時にアピールできる
就職・転職希望者の持つ技術や知識を、職歴や経験だけで正確に判断することは大変難しいとされています。経験豊富な人材であってもその現場で必要な業務を的確にできるとは限りません。人事や採用の担当者はその人材の持つ能力を慎重に見極めて採用を判断します。
そうした転職市場において、機械のメンテナンスの技術や知識を客観的に証明できる国家資格を保有しているということは、非常に大きなアピールポイントになります。就職や転職活動を有利に進めやすくなる可能性が高まるでしょう。
キャリアアップにつながる
企業によっては、昇格・昇進要件に機械保全技能士の資格取得が含まれている場合もあります。実務経験に応じてより上位の資格を取得し、より重要な業務を任される機会が増えれば、
主任・係長・課長とどんどんキャリアアップし現場を統括する管理職の立場を目指すこともできるでしょう。
資格手当がもらえることも!
製造メーカーの中には、機械保全技能士の資格に対して資格手当を支給しているところもあります。
支給される資格手当の金額は企業によって異なりますが、通常の給与に上乗せで手当てを受け取れるようになれば、毎月の給与がアップし実質的な昇給が叶うこととなります。
機械保全技能士に求められること
機械に不具合が生じて生産力が低下しないよう、工場の設備機械の定期点検やメンテナンスを行うことが機械保全技能士の基本的な役割です。いわば「工場機械のお医者さん」とも言えるでしょう。
機械の不具合を防ぐためには、機械の種類ごとに適した手順とスケジュールを策定し、点検を実施する必要があります。機械自体に関する幅広い知識はもちろん、機械の稼働状況や現場の状況などを総合的に見て計画を立てるため、計画性や判断力も求められます。
また部品の微細な傷や劣化、異常に気付く観察力や、予期せぬトラブルが起こった際に迅速に対応する柔軟性も機械保全技能士に求められるスキルです。
機械保全技能士に向いている人の特徴
「機械保全技能士に興味はあるけれど、自分に向いているか分からない…」
そんな方に向けて、機械保全技能士に向いている方の特徴を4つご紹介いたします。


機械や設備に興味がある
どんな仕事でもそうですが、興味がある分野は覚えやすくスキルも身に付きやすいことが多いです。
機械を分解して仕組みを見るのが好きだったり、自分でパーツを揃えて組み上げるのが好きだったり…そんな方はまず第一に、機械保全技能士としてとても適性があると言えます。
判断力・対応力に自信がある
機械や設備は、予期せぬトラブルが発生する場合があります。その際に重要なのは、冷静に判断して対処できる力です。
トラブルに遭遇しても感情的にならず落ち着いて、周りと協力しながら解決を考えられる方は機械保全技能士に向いている可能性が高いと言えるでしょう。
コミュニケーション力がある
機械保全技能士の業務の多くは、1人では完結しません。他の業務を行っている従業員と協力しながら作業を進めていくため、コミュニケーション能力は欠かせない能力の1つです。
チームで何かに取り組むことが好き、相手の立場になって論理的に説明することが得意という長所は、機械保全技能士に向いている特徴の1つです。
計画を立てるのが好き・得意
機械保全技能士の業務のメインである機械のメンテナンスは、工場の生産ラインに可能な限り支障が出ないよう、先々まで予定を立て計画的に行います。
スケジュールをしっかり立て、それに沿って行動したい…そんな方は、機械保全技能士の業務で力を発揮できる可能性が高いです。
機械保全技能士に関するよくある質問(FAQ)
Q 機械保全技能士は本当に役に立たない資格ですか?
Q 機械保全技能士はどの級から取得するのがおすすめですか?
- ・3級:基礎的な知識・技能を証明
- ・2級:中堅レベルの技能を証明
- ・1級:高度な知識と技能を証明
- ・特級:管理監督者レベルの技能を証明
Q 機械保全技能士の合格率はどれくらいですか?
| 等級 | 合格率(参考値) |
| 特級 | 約20~30% |
| 1級 | 約30%前後 |
| 2級 | 約40%前後 |
| 3級 | 約70%以上 |
参照:厚生労働省 令和6年度「技能検定」の実施状況(合格率:45.2%)
Q 転職で機械保全技能士は有利になりますか?
Q 機械保全技能士に向いている人の特徴は?
- ・機械や設備の仕組みに興味を持っている人
- ・計画的に作業を進めることが得意な人
- ・トラブル発生時に冷静に原因を分析できる人
- ・現場でチームと協力して取り組める人
機械保全技能士の資格を活かして働くならものっぷへ!
国家資格である機械保全技能士は、製造現場で非常に重宝される資格です。取得したらぜひ、資格を活かして活躍できる現場で力を発揮してくださいね!
「機械保全技能士の資格を取るために実務経験を積みたい」という方は、製造業に特化した求人サイト「ものっぷ」への登録がオススメです。ものっぷは未経験から設備保全にチャレンジできるお仕事がたくさんあるのが大きなポイントの1つ。工場の仕事が初めてという方や、他業種からの転職を考えている方も、ゼロから機械保全技能士に向けての一歩を踏み出せますよ。
もちろん、機械保全技能士の有資格者向けのお仕事も豊富にあります。ぜひものっぷであなたの力を発揮できるお仕事を探してみてください。
関連記事はこちら:
▶ 資格を活かして働きたい方へ
「機械保全技能士」をはじめとした資格を活かせる求人を多数掲載しています。
資格を活かせる求人一覧はこちらからチェック
さらに、非公開求人やキャリア相談などのサポートを受けたい方は、ものっぷへの無料登録がおすすめです。資格を強みにした就職・転職活動をより有利に進められます。



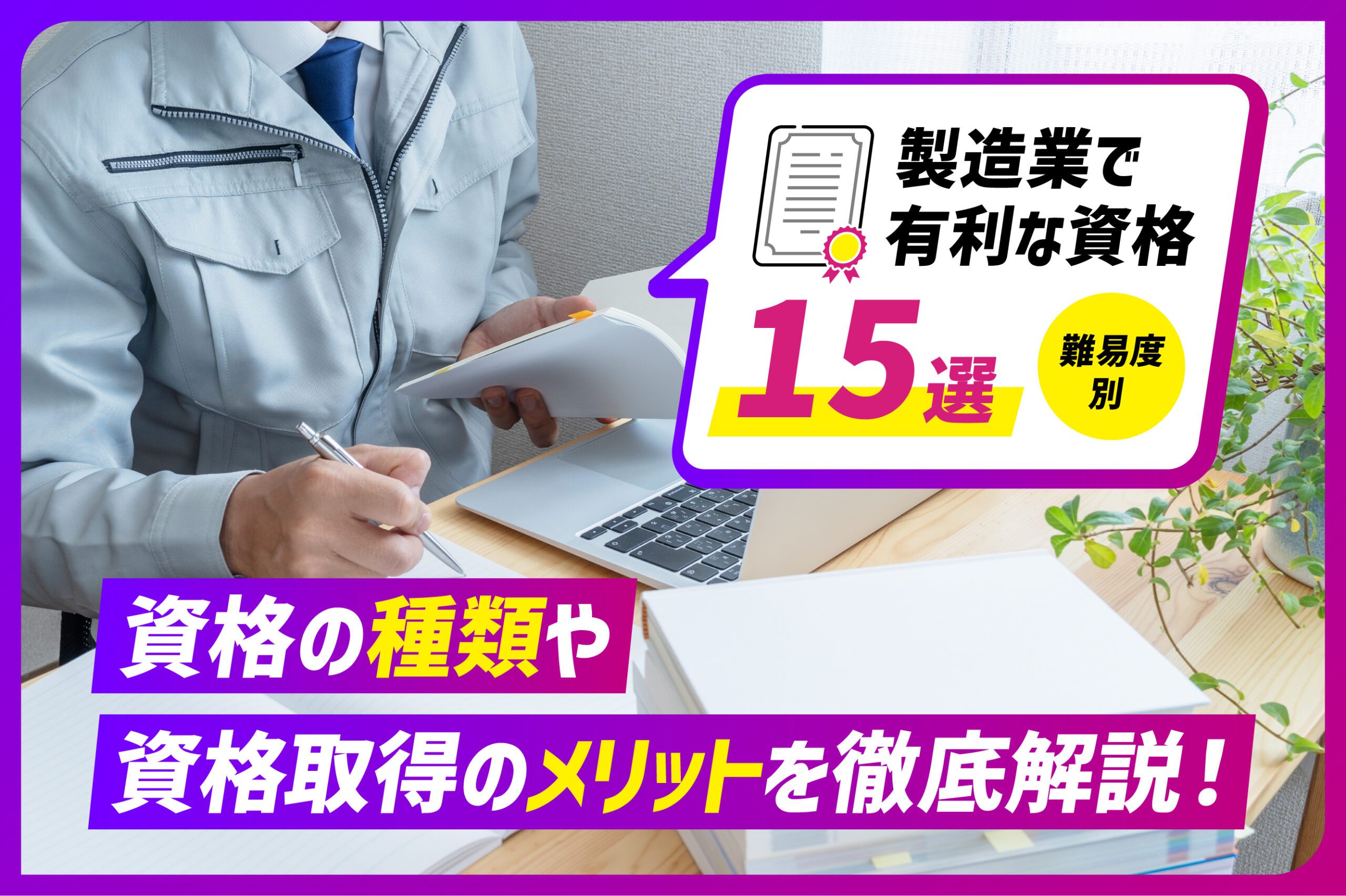
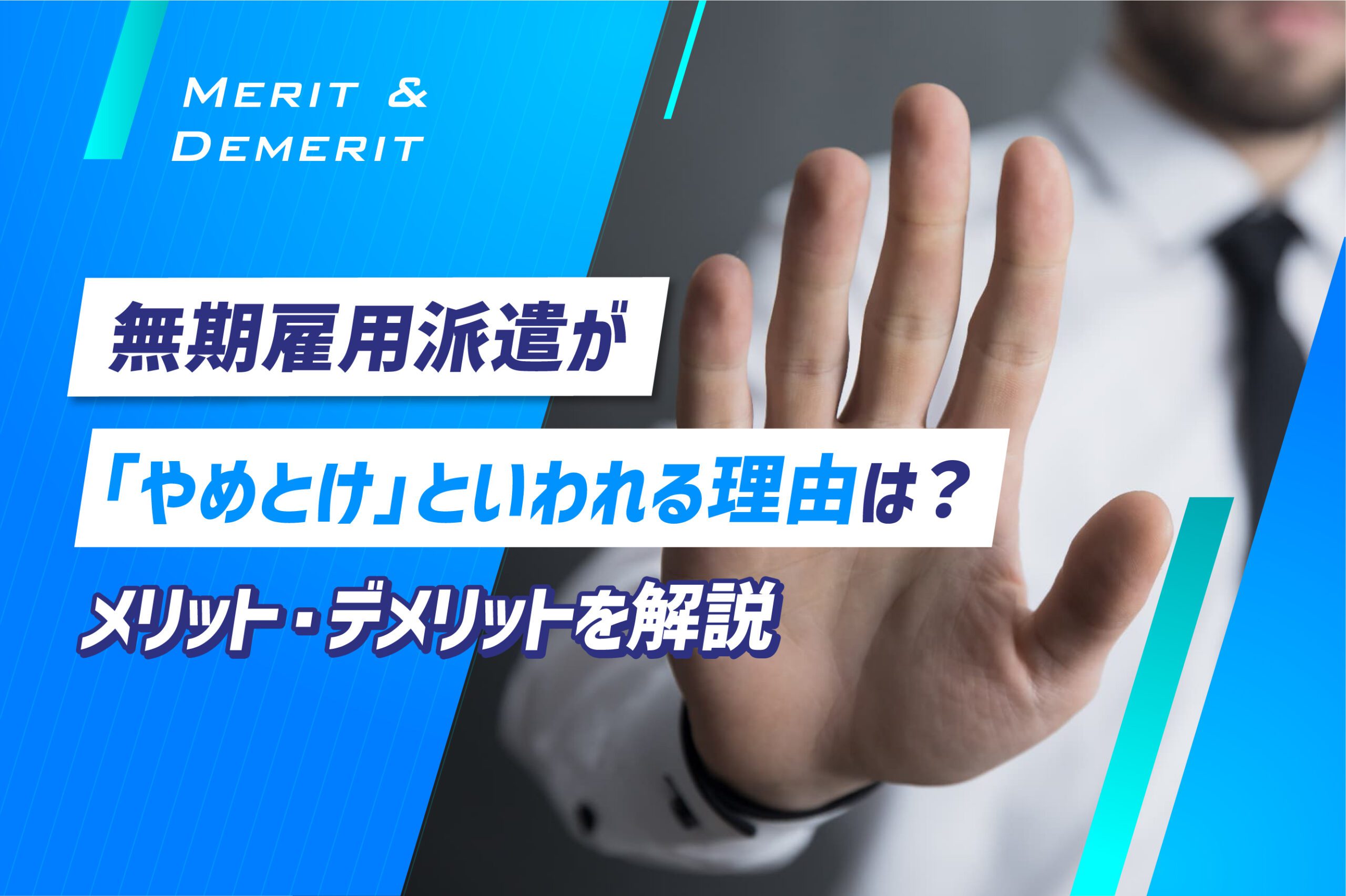


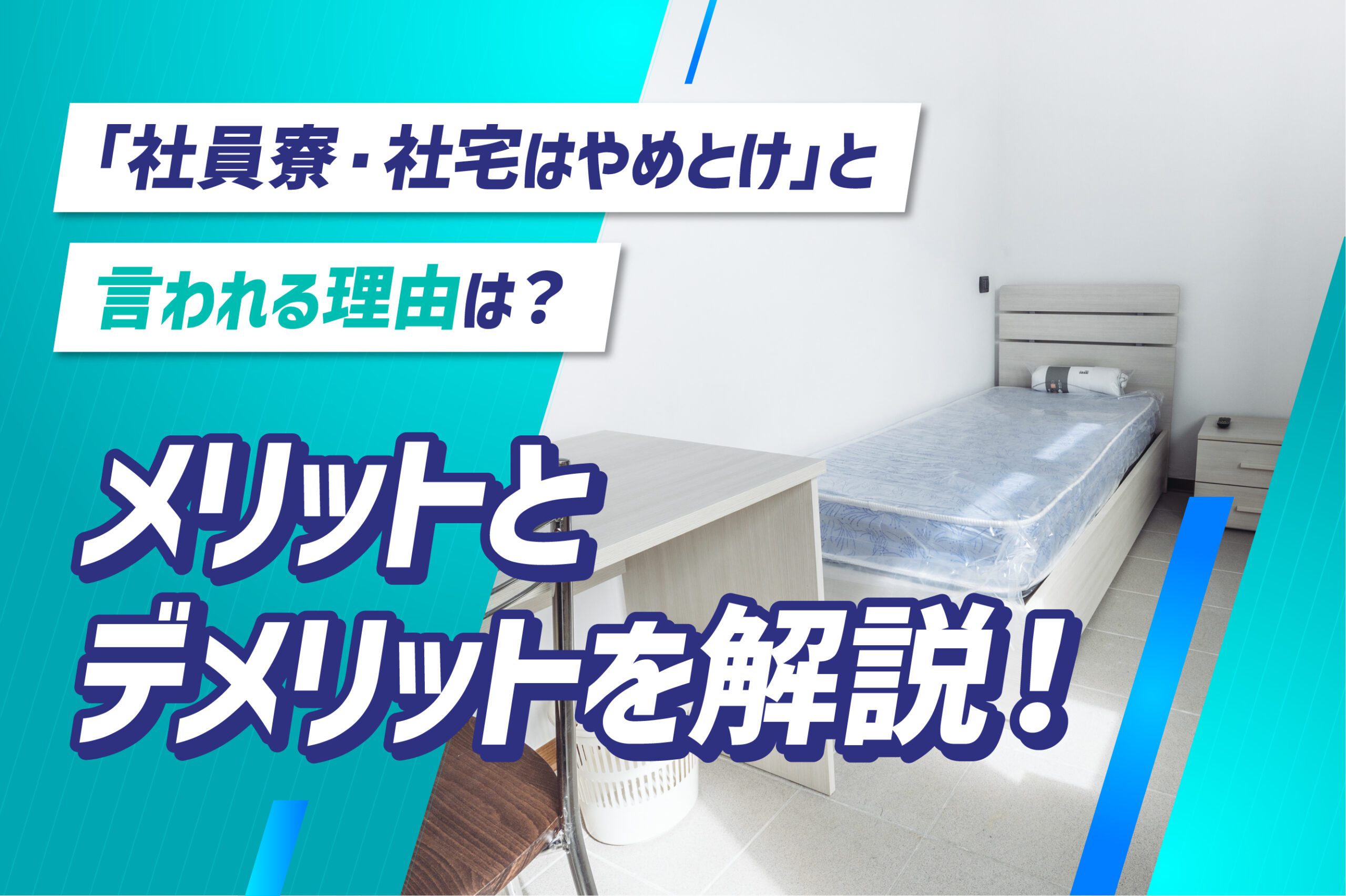

【寮付き求人は怪しい?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-1月.jpg)
【フォークリフトはどんな種類がある?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-1月.jpg)
【期間工で働くデメリットは?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-1月.jpg)
【人と関わらない仕事って何?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-1月.jpg)
【工場勤務で副業は可能?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-1月.jpg)

【倉庫内作業の志望動機はどう書くの?】-ものっぷなびーコラム-サムネイル画像-11月.jpg)



